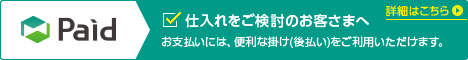近年、農業の世界でもAIやロボットを活用したデジタル化が進んでいることをご存じでしたか?
農業×デジタル化は、農業の世界で起きている問題を解決へと導くと期待されているため、今後切っても切れない関係になっていくでしょう。
ここでは農業におけるデジタル化はどういったものなのか、日本や世界でどんな風に実践されているのか解説していきましょう。
農業のデジタル化とは?

AIやロボットを使った次世代型農業はスマート農業(スマートアグリ)と呼ばれており、昨今世界中から注目を浴びています。
海外ではスマート農業のことをアグリテックとも呼ばれており、試験から導入まで日本よりも進歩しています。
スマート農業については、農林水産省によって以下のように定義されています。
「ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する等を推進している新たな農業のことです。」
引用元:農林水産省
つまり、これまで人に依存していた農業を、これからは機械やシステムといった技術を活用して、‘‘省エネルギー‘‘で‘‘品質のいい作物‘‘を‘‘多収‘‘にしていくことを1つの目的としています。
農業のデジタル化で何が解決するの?
農業のデジタル化によって解決する問題は主に以下の3つです。
・人手不足や属人性
・高齢化問題
・食料自給率
それぞれ詳しく解説していきましょう。
人手不足や属人性
農作業は機械化が進んだ今でも人の手やベテラン農家さんも技術や知識に依存しています。スマート農業の導入によって誰でも同じレベルで、かつ省力化して農業が行えるようになります。
高齢化問題
農林水産省の調査によると、令和2年度の農業従事者は約136万人でその中で60歳以上は69万人と半分以上を占めています。
農家の平均年齢は67.8歳と高齢化が進んでおり、年々農家が減っています。これによって1人当たりの農地面積が広くなっていることも農業問題の1つです。
これらの問題もICTなどのデジタル化で1人当たりの負担軽減と作業効率があがるため、解決できます。
食料自給率
日本の食料自給率は2020年度の調査では37%(カロリーベース)と自国では国民の食料を半分も生産できないことが明らかとなっています。
ロシアウクライナ戦争によって、いかに輸入頼りが危険かということは十分に認識できたかと思います。
これらの問題はロボットによる自動化で作業効率UPや、植物を作る専門工場などで解決していきます。
デジタル化の導入例

実際に行われているAIやロボットを駆使したスマート農業の実例を紹介していきましょう。
ドローンを使った農薬散布
大規模な農場においては、手作業での農薬散布は人手と多くの時間が必要なため、ヘリコプターを使った農薬散布が行われている地域があります。
しかし、ヘリコプターは機械が大きく操縦が難しいため、扱うには経験と技術が必要です。ドローンであれば、小型で軽量、そして小回りがきき、操作も比較的簡単なため、ヘリコプターよりも扱いやすいです。
さらに、GPSを備えたタイプは自動操縦が可能で、操縦者が見えない場所へも農薬をまくことができます。
また、カメラで上空から農作物の生育状況を確認することも可能です。
自動走行トラクター
自動走行トラクターとは、無人トラクターとも呼ばれるもので、スマート農業を普及させる上で欠かせないものとされています。
このトラクターは、専用のタブレットで登録した農場と、これまでの走行データに基づいて自動で走行します。
作業中のトラクターは専用のタブレットで操作できるため、遠隔で作業を行うことができます。
耕うんから肥料散布、代かきなどトラクターでできる作業はだいたい可能なため、作業負担の大きな軽減になります。
AI自動認識収穫システム
AI自動認識収穫システムとは、イチゴやリンゴ、ナシなど果実の熟成度をAIが自動的に判別して収穫していくシステムのことです。
AIのディープラーニングによって、判別の正確度は90%以上を達成しています。このシステムと自動走行車両を接続すれば、無人で収穫ができるようになります。
世界のスマート農業~オランダ編~
日本でも農業のデジタル化は進んでいますが、多くの農家はまだ以前と同じような農業スタイルのままです。一部の大規模農家しか、スマート農業を実践していません。
世界に目を向けると、オランダは特にスマート農業の普及が広く進んでいます。
そこでオランダのスマート農業について紹介していきましょう。
農業のデジタル化を推進したことで世界第二位の農業大国に
オランダの農地は、日本の半分以下でありながら農産物の輸出額はアメリカに次ぐ世界2位という地位を築き上げてました。
1980年代のECに加盟していた時代、貿易の自由化によって国内の農業が苦戦を強いられることになりました。そこから巻き返しを図るべく、スマート農業の推進に舵を切りました。
今となっては、オランダの農家の8割ほどがAIやICT、ロボットを使ったスマート農業を実施しています。
オランダの農業はデジタル化によって農業大国に名乗りをあげることとなったのです。
オランダのスマート農業の特徴とは?
オランダのスマート農業で特に有名なものは、ビニールハウスを使った栽培方法です。
アグリポートA7と呼ばれる巨大なビニールハウスでは、最新のテクノロジーを使った徹底した管理を行っています。温度、湿度はもちろん、光量、二酸化炭素濃度など作物が育つうえで影響があるものをセンサーを使って検知します。これら1つ1つを管理、制御するのではなく、トータルで判断しています。
天候や気温が野菜にとって良くない環境の時は照明や暖房で条件を整えています。
野菜にとって最適な環境を24時間体制で作り上げているため、天候に左右されることなく、良質な野菜をたくさん作ることが可能になっています。
日本のスマート農業は広まる?
ここまで農業のデジタル化について紹介してきました。それでは日本のスマート農業の行方はどうなっていくのでしょうか?
結論から言えば、日本においてスマート農業の普及にはまだまだ時間がかかるでしょう。
その理由について、日本の現状と課題から解説していきましょう。
イニシャルコストが高い
スマート農業が広まらない大きな要因としてはコストの問題です。
無人トラクターの場合、1台当たりの価格は最低でも1,000万円です。このトラクターを購入できる農家は数少ないでしょう。
その理由は農地面積にあります。日本の農業従事者1人当たりの農地面積は平均1.8haですが、アメリカは約113haと63倍ほど差があります。
農地面積と農業での収入は比例するので、農地面積の小さい日本ではスマート農業の普及はなかなか簡単にはいかないでしょう。
体制作りが重要
スマート農業が普及するためには体制づくりが重要です。
農家にはスマート農業を伝えていくための人材が必要です。高齢化が進む農家さんに機械の使用方法を伝えていくのには時間と人手がかかります。スマート農業をする方へのサポート体制やサポートできる人材の育成が必要です。
また、補助金の制度も重要です。
消費者にも認知が必要
日本では、ロボットで作った野菜よりも人の手で作った野菜の方が美味しいというイメージがあります。実際のところ、まだまだ熟練者の方が美味しい野菜を作っています。
まずはスマート農業で一定以上の品質、かつ多収量をあげるようにし、そのあとロボットが作った野菜も美味しいということを消費者に広く認知させていくことが重要です。
これからのスマート農業に注目しよう!

現状はまだまだ広まっていないスマート農業ですが、農林水産省が先頭に立って農業のDXを進めています。
日本の農業はさまざまな問題を抱えているため、国を挙げて解決へ動いていかないといけないのは明白です。
世界では人口が年々増加しています。今後食糧危機が訪れると予想されているため、日本のスマート農業が広く認知されていけば、これまでの輸入頼りから一転し、世界へ輸出していくことが可能になるかもしれません。
国の動向を見つつ、これからのスマート農業に注目していきましょう!